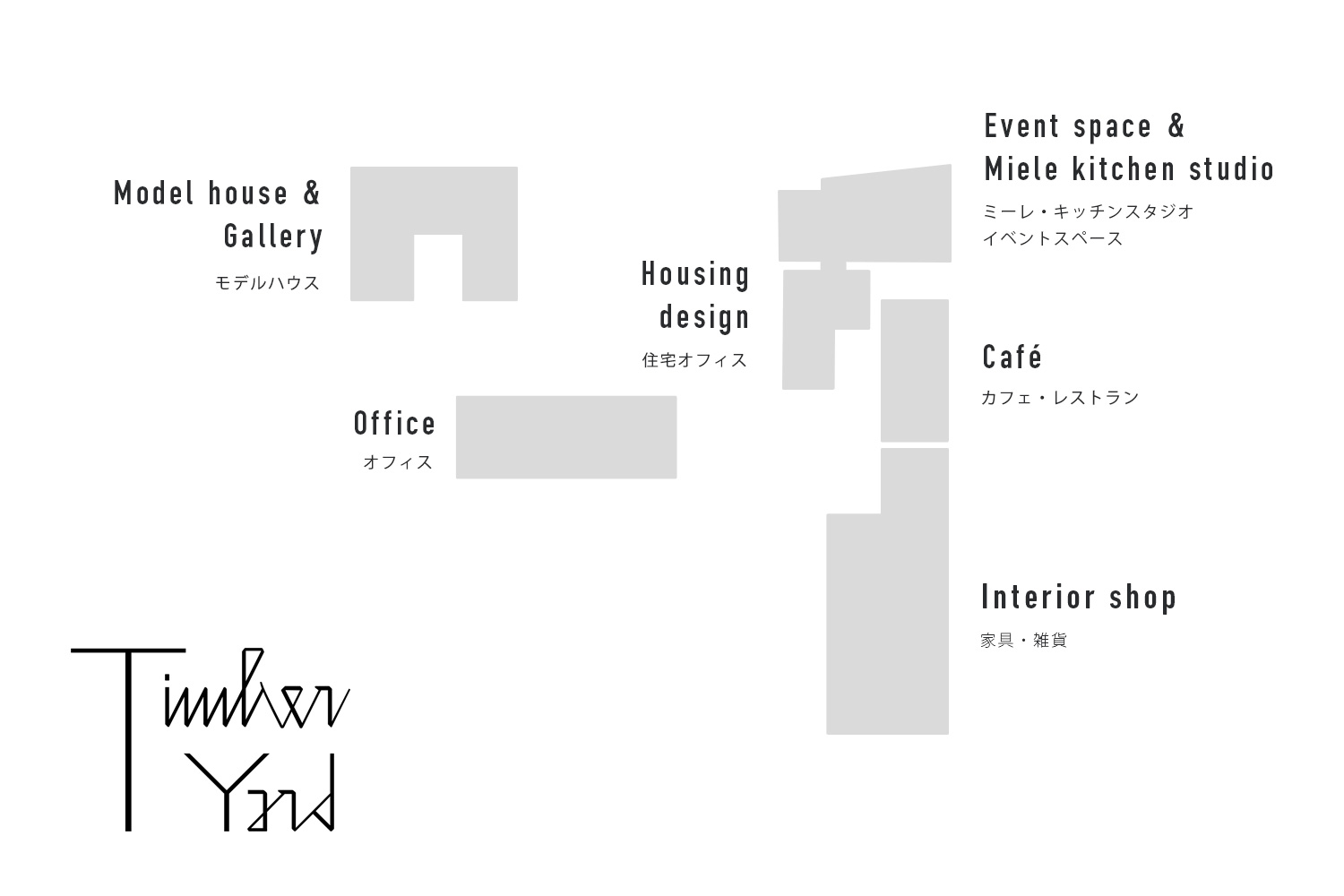「擁壁(ようへき)」と聞いても、いまいちどんなものかイメージできない人も多いのではないでしょうか。
擁壁はただの壁とは違い、土砂から家や道路などを守るためにあります。
命と財産を守る大切な擁壁ですが、中には劣化が進んでしまい、機能を果たせていないものも少なくありません。
自宅や自宅付近の擁壁が安全かどうかを知る目安として、擁壁の種類・仕組みについての基礎知識を学んでおきましょう。
目次
擁壁とは?

擁壁は、隣り合った土地同士で高低差がある場合、高い位置から低い位置へと土砂が崩れてしまうのを防ぐ「土留め」としての役割を持っています。
坂道の途中にある家などは、家を斜面に合わせて、斜めに建てるわけにはいきません。
そこで、家が水平になるよう土をたいらに盛ったとします。
しかし、坂道をくだればくだるほど、盛った土と坂道に高低差ができてしまいますよね。
むき出しの盛った土が坂道のほうに流れてしまえば、家を水平に支えることができなくなり、坂道も使えなくなってしまいます。
擁壁は低い方・高い方、両方にある建物や土地を守るために存在しているのです。
ただの壁とは違うの?
壁と擁壁の違いは、
- 隣り合った土地同士に高低差があるかどうか
- 土を受け止めているかどうか
平らな土地にあり、外部からの視線を仕切る目的で建てられたのが壁です。
擁壁はL字・逆T字の形で地面の中に土台があります。
支えている土自体を土台部分の重しとして壁を自立させ、建物と土地を守っています。
本立てを想像すると、わかりやすいでしょう。
擁壁の種類

擁壁にはさまざまな種類があります。
なかには、現行法の基準に満たないタイプもあるため、物件探しの際は注意しましょう
RC造(コンクリート)
RC造の擁壁は、なかに鉄筋が入っているタイプとそうでないタイプの2つがあります。
RC造の擁壁の形は、おもに下記の5つです。立地条件によって使用するタイプが異なります。
- 逆T型擁壁
隣接する土地との境界線が広い場合に用いる。土台部分の土と擁壁自身の重さで土圧に耐える。 - L字擁壁
隣接する土地との境界線が狭い場合に用いる。本立てをイメージするとわかりやすい。 - 逆L字擁壁
擁壁の背後に建造物といった障害がある場合に用いる。L字擁壁と反対側の面で土を支える。 - 重量擁壁
逆T字・L字・逆L字よりも擁壁部分が厚い。無筋RC造。自身の重さで土を支える。 - もたれ式擁壁
支える土によりかかるようにして、ななめにもたれかかった擁壁。
間知ブロック
「間知ブロック擁壁」とは、四角いブロックをジグザグ、もしくはレンガ調に積み上げた擁壁です。
ジグザグに積んだのを矢羽積、レンガ調に積み上げたものを布積といいます。
高さ5メートルまで積み上げられるため、山の斜面などでも使える擁壁のタイプです。
そのほか、高低差のある住宅地でも見かけます。
大谷石積み
「大谷石積み擁壁」とは、その名のとおり、「大谷石」と呼ばれる石を積み上げた擁壁です。
大谷石は水通りが良いですが、経年劣化がしやすいのが弱点。
1950~1960年代に建てられた住宅でよく見かけますが、現行の法律では基準を満たしていない擁壁です。
空石積み
「空石積擁壁」とは、石を積んだだけの擁壁です。
コンクリートや砂利などの基礎が入っていますが、RC造や間知ブロックに比べてかなり壊れやすく、1.5m以上の高さの土は支えられない可能性があります。
こちらも大谷石積み擁壁同様、現行法の基準を満たしていません。
二段擁壁
「二段擁壁」とは、RC擁壁や間知ブロック擁壁の上に、さらにコンクリートブロックを置いて擁壁部分を伸ばしたタイプの擁壁です。
通常の擁壁と違い、伸ばした部分は土圧に耐えられるだけの土台がありません。
非常に危険なため、現行では違法扱いとなります。
擁壁に関する法律

擁壁に関しては、法律で定められた規定があります。
下記に、建築基準法施工令の第142条(擁壁)に関する内容の一部を抜粋します。
第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
引用元:e-Gov 法令検索
とてもわかりにくく書いてありますが、要約すると…
- 鉄筋コンクリートや石といった腐食しない材料で作ってね
- 石の場合はコンクリートをしっかり詰めて、石と石をくっつけてね
- 排水のための水抜き穴をつけて、擁壁裏の水抜き穴は排水できる材料を置いてね
- この3つと同等か、それ以上の安全レベル基準を満たした擁壁を作ってね
という内容です。
プロは把握している法律ですが、一般の人であればとくに知る機会もないかと思います。
そのため、知識がないのを良いことに、足元を見るような施工会社もあるかもしれません。
擁壁に関する正しい法律の知識を身につけておくことで、最適な擁壁施工をしてくれる会社を見つけやすくなるでしょう。
擁壁の注意点
擁壁は一見何の問題がないように見えて、さまざまなトラブルを引き起こしやすい存在です。
擁壁付きの物件を購入予定、もしくは現状で擁壁のある物件に住んでいる場合、次のことに注意をしましょう。
中古物件の場合「既存不適格擁壁」の可能性
古い物件の場合、擁壁が現行法の基準を満たしていない可能性があります。
「すぐに擁壁を建て替えなくてはいけない」というわけではありませんが、住宅をリフォームするときには擁壁も現行法に合わせた作り替えが必要です。
新築でも安心しない
新築の家でも、擁壁のトラブルは多いです。
擁壁は歳月とともに劣化します。
新築物件であっても建設から時間が経っているのであれば、そのぶんだけ擁壁にも影響が出ているでしょう。
近隣トラブルの元になりやすい
擁壁は近隣との境界に建てられる場合がほとんどなので、ご近所トラブルの元になりやすいです。
例えば、お隣が何らかの理由で盛り土をしたことで、古い擁壁が崩れかけてしまったという場合です。
擁壁の所有者と盛り土をしたお隣、どちらが修繕費用を出すのかで、揉め事に発展する可能性が高いでしょう。
また、通常であれば擁壁は高いほうの敷地が所有者であるため、建設義務があります。
しかし何かしらの経緯で、低い敷地と折半をして建設するパターンも少なくありません。
歳月が経過してそれぞれの家の所有者が世代交代をしたとき、擁壁の修繕費を再び折半できるのかどうか、話し合わなくてはなりません。
擁壁にかかる費用の決め方
擁壁の建設費用は事前の見積もり段階では、はっきりとした金額が出せない場合が多いです。
現地調査をしないことには、何がどのくらい必要なのかわからないからです。
では、擁壁の金額を決める目安とは何なのでしょうか。
住宅の立地条件
まず、住宅の立地条件によってどのような形で土を止めれば良いのかを決めます。
近隣との境界線の位置・高低差などが、擁壁のタイプ決めの目安の一つです。
さらに住宅に建設するのか山道なのか、まわりの土地の景観を壊してしまわないかなど、環境面も考慮して最適なタイプを決めることが多いです。
なにで擁壁を作るのか
擁壁を作る場合、RC造にするのか間知ブロックにするのかなど、擁壁の材料によって金額が変化します。
RC造では中に鉄筋を入れるのかどうかも、金額決めのポイントとなるでしょう。
擁壁の面積
同じタイプの擁壁を同じ場所に建てたとしても、どの程度の高さ・幅が必要なのかで金額は変化します。
当然、面積が大きくなればそのぶんだけ金額があがります。
擁壁の安全性を確かめるチェックポイント

擁壁の安全性について不安を感じる人も多いと思います。
擁壁の安全性の目安となるポイントについて、詳しく見てみましょう。
水抜き穴があって排水は良好か
擁壁には通常、水抜き穴があります。
水抜き穴がなく排水がきちんとできていないと、擁壁にのしかかる土が水を吸ってしまいます。
その結果、擁壁にかかる土圧があがり、ひびや破損の原因になります。
水の染み出しがないか
水の染み出しは一概に「すべて問題アリ」とも言えません。
劣化の有無は関係なく、地下水位が高くなったり、雨などで擁壁自身に浸透した水が染み出ているだけだったり、という場合もあります。
擁壁の劣化による水の染み出しなのか判断が難しい場合は、プロに調査依頼をしたほうが結果としてコスパが良くなるでしょう。
擁壁の素材と構造
擁壁のなかには、現行法の基準を満たさない材料を使ったものや構造方法のものがあります。
すぐに建て替える必要がなくても、将来的に問題が出てくる可能性が高いです。
国土交通省のチェックシートがおすすめ
擁壁の安全性チェックには、国土交通省が公開している「我が家の擁壁チェックシート(案)」が便利です。
気になる方はチェック!
擁壁の耐用年数は?
擁壁の耐用年数は、RC造であれば30~50年ほどです。
擁壁の厚みや立地環境、排水の有無や気候などでも差があります。20年を越えたあたりから劣化が進行しやすく、危険性も大きく上がるため注意が必要です。
該当する築年数の擁壁を所持している人は、専門家に1度診断してもらいましょう。
自宅や購入予定の家の擁壁チェックは欠かさずに

今回は擁壁の基礎知識について解説しました。家を購入するときは、つい建物本体にばかり目がいってしまいがちです。
しかし擁壁はその大切な建物自身を守るためにあります。
擁壁としての基準を満たしているのか、劣化は見当たらないかをきちんとチェックしておきましょう。
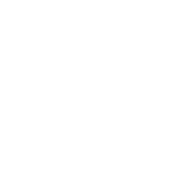

![cozy life[コージーライフ]](https://timberyard.net/cozylife/wp-content/uploads/2020/10/cozy-life.png)